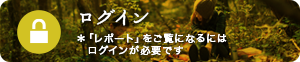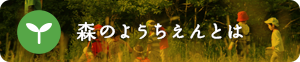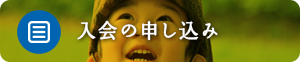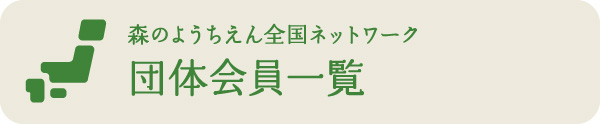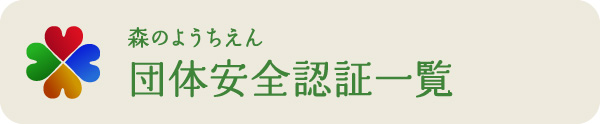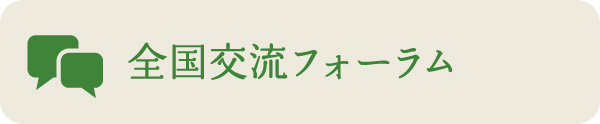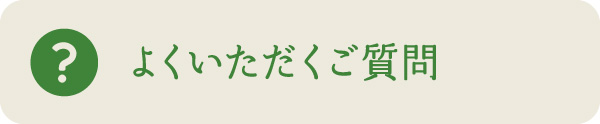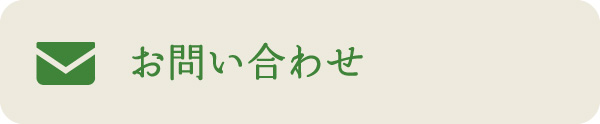馬と子どもと暮らしのあいだにあるもの──三陸駒舎の日常を映像でまとめました
三陸駒舎で毎日くり返されている、馬との暮らしや子どもたちとの時間を、そのまま映像にまとめました。
古民家を拠点に、馬の世話をしたり、川へ行ったり、山で遊んだり、畑を見にいったり。
子どもも大人も一緒に動きながら、その日その時の場が流れるようにつくられていきます。
今回公開した2本の映像は、三陸駒舎の「考え方」や「方針」を説明するものではありません。
それよりも、日々のなかで起きている“変化の種”のようなものを拾った映像です。
保護者の目にうつる子どもの姿、スタッフが感じている馬との距離、そして環境が子どもをどう包んでいるのか。
森のようちえんの実践に関わる方々にとって、
「場の空気がどう立ち上がっているか」
「子どもの変化を、日常の積み重ねからどう拾えるか」
を考える手がかりにもなる映像になっています。
では、2本の映像の内容を簡単に紹介します。
子どもを見守る“場の力”を語る映像 ― 保護者篇
この映像は、三陸駒舎に通う子どもたちの保護者が語り手になっています。
それぞれの家庭から見える「変化の芽」がいくつも含まれています。
「ここだと喧嘩しても引きずらないで、次に会った時には普通に過ごしている」
「切り替えが難しかった子が、ここでのリズムがあることで、自分という輪郭が整ってきている」
「虫が苦手でも、キャンプがあると言うと二つ返事で行く」
「初めて会う子にも“それ危ないよ”と声をかけているのを見て、考えて動けていると感じる」
これらの語りは、
“自然と馬が媒介することで、子ども同士の関係調整がどのように生まれるのか”
という点を示しています。
ここでは、
「子どもの変化を、家庭の視点からどう受け取っているか」
がそのまま語られており、現場のスタッフとは違う角度から“場の働き”が見える構成になっています。
大人が学び直している現場としての三陸駒舎
こちらはスタッフが語る映像です。
馬といる時間が、大人のほうにも働いているという視点が印象的です。
「馬がいなかったら続けられなかった。半分は大人のために馬がいる感覚がある」
「子どもと関わる時のコミュニケーションを馬から学んでいる」
「お世話の時間になると、子どもたちが自ら“じゃあ僕これやる”と動き出す」
「固定観念がない状態で動く子どもの姿から、こちらが学ばされる」
スタッフたちが語るのは、
“支援する側”としての視点ではなく、
“この場にいる大人としての経験”です。
川、山、畑、田んぼ、古民家。
動ける場所が多いことが、子どもの選択肢を自然と増やしているという話もあります。
遊びと暮らしがそのまま混ざっていて、特別なプログラムをしているというより、「一緒に過ごしている」状態に近いという語りもあります。
映像が伝えているのは、“特別な体験”ではなく“日常そのもの”
この2本の映像に共通しているのは、どちらも「特別なイベント」や「成果」を見せようとしていないことです。
そこにあるのは、毎日の暮らしの流れのなかで生まれた、大小さまざまな変化です。
馬の存在が、子どもにも大人にも作用していること。
自然の広さが、遊びと学びの境界をなくしていること。
保護者のまなざしが、子どもの変化を拾い上げる大事な手がかりになっていること。
森のようちえんの実践に携わる方や、自然に関わる場をつくっている人にとって、
「場のつくり方を言葉で説明しなくても伝わる資料」
として利用できる内容になっています。
この場に関わりたい方へ ― 三陸駒舎からスタッフ募集の案内
映像で紹介したように、三陸駒舎では、馬との暮らしを軸にしながら、子どもたちと地域の時間を積み重ねています。
馬の力に頼り、子どもの成長を支援するホースセラピーのスタッフ募集しています。
ホースセラピーや子ども支援の経験は問いません。
馬と暮らす毎日の中で学びながら、子どもたちと向き合い、地域の自然の中で働く形を整えています。
詳しい募集内容やオンライン説明会の案内は、こちらのページでまとめています。
→ スタッフ募集の詳細はこちら