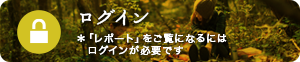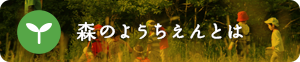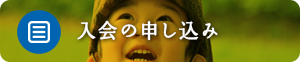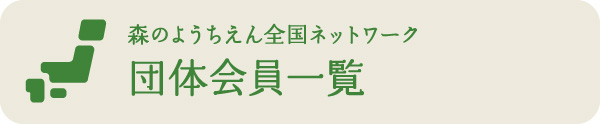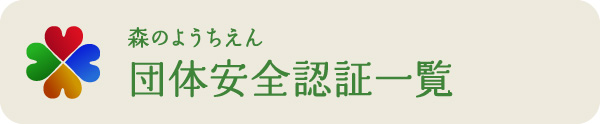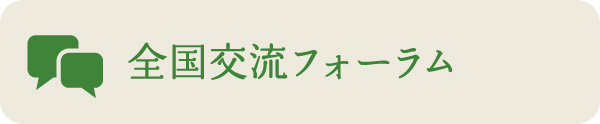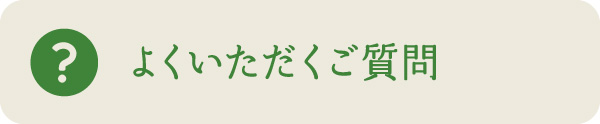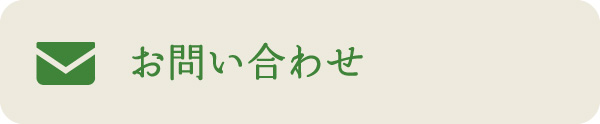【感覚統合 × 森のようちえん】の魅力〜自然が子どもの七つの感覚を育む
2025年2月18日
森のようちえんは、自然の中で子どもたちが主体的に遊びや活動をすることで、心身の成長や学びを深める保育・教育のスタイルです。近年、発達支援の理論のひとつとして注目されている「感覚統合理論」を合わせて取り入れることで、子どもが自然の中で得る体験の幅はさらに広がり、子ども自身の持つ「生きる力」をより伸ばすことができるとされています。
感覚統合の理論を森のようちえんの活動にどのように活かせるのか、コラムを作成ました。森のようちえんの活動を深め、子どもの育ちをより良いものにする視点が得られると思いますので、ぜひご一読ください。
感覚統合理論(Sensory Integration:以下 SI)では、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)に加え、“前庭覚(揺れやバランス、傾き)”と“固有受容覚(筋肉の収縮や力の入り具合)”を含めた計7つの感覚を重視します。森のようちえんの自然豊かな環境は、まさにこの7感をフルに刺激しながら、子ども自身が主体的・探究的に活動できる点が大きな特徴です。
コラムでは、以下の流れ沿って解説していきます。
- 森のようちえんの概要と子どもたちが得る体験
- 森のようちえんとは
- 子ども自身が主体となる保育・教育
- 自然の持つ多様性と変化
- 感覚統合理論の基本と七つの感覚
- 感覚統合理論とは
- 七つの感覚
- 感覚の個人差と“困り感”
- 森のようちえん×感覚統合がもたらす具体的なメリット
- 五感+前庭覚+固有受容覚をフルに使う遊び
- 子どもが「自分で選ぶ」ことで高まる内発的な学び
- 感覚統合の視点から見る「安心感」と「自己効力感」
- 失敗と衝突を通しての学び
- 感覚統合の視点をより活かすためのヒント
- 子どもの感覚特性を観察し、必要に応じて調整する
- 遊びのなかでのアイテムや環境の工夫
- 大人の関わり方のポイント
- 森のようちえん実践者へのメッセージ
- 無理やりの「感覚統合」ではなく、子どもが主体の遊びを大切に
- 子どもをよく観察し、適切な環境を用意する
- 大人自身も「自分の感覚」を知る
以下のページには、感覚統合を解説したポッドキャストもご案内しています。合わせてお聴き下さい。
五感は古い 七感で子どもは育つ!「感覚統合×馬・自然体験」を知るためのガイド
音声配信ネットラジオ 毎週更新 〜ホースセラピーや子どもとの関わり方をお届けします〜
ホースセラピー、馬との暮らし、子どもとの関わり方などを三陸駒舎の現場から届けます。
以下からもお聴きいただけます。
全国で教育的な牧場を経営する寄田と復興まちづくりに携わる黍原を中心に2015年4月に設立。築90年の古民家を拠点に、馬と共に暮らす地域文化をベースにエコツーリズムやホースセラピーなど新たな仕事を起こし、誰もが心豊かに過ごすことのできる持続可能な地域の未来をひらきます。2017年の年より障害児を対象としたセラピー事業も開始。